"あじわい"の不思議『薩摩心酔 力三』

はじめに
地域ブランド『薩摩のさつま』の認証品を生み出す作り手の方を訪問し、商品が生まれた背景や風土をお届けするシリーズ。
今回お話を伺ったのは、焼酎『薩摩心酔 力三』を作る小牧醸造株式会社 代表取締役社長の小牧 一徳さんです。
“あじわい”という言葉の不思議。多くの人の手によって形づくられ、さらに世代を越えるあじわいとは…。

聞き手:青嵜(以下省略)
――さつま町で蔵元を営む”小牧醸造株式会社”さんの認証品『薩摩心酔 力三』。
2019年にはさつま町(旧宮之城町)で創業110周年を迎えたという老舗の蔵元としてのお酒造りや認証品、そして町や未来への想いを、代表取締役社長の小牧一徳さんにお話をお伺いします。
まず最初に、小牧醸造さんが普段されているお酒造りについて、どういった流れで年間のお仕事をされているのか教えていただけますか?
小牧 一徳さん(以下省略)
うちは生芋にこだわった芋焼酎をメインで造っていますので、基本的には、8月の盆明けからスタートして12月いっぱいまでっていうのが製造期間になります。
なんでかって言うと、主原料の芋の収穫時期が通常だと8月後半から9月ぐらいに収穫されるからなんですけど、そこから始まって、まあ12月頭には霜が降りて根腐れしてしまうので、それまでに収穫して12月いっぱいで製造を終える流れになります。

で、それとは別に、例えば米焼酎や麦焼酎っていうのは時期が決まっていないので、芋焼酎造り以外の時期に作っています。
あと焼酎ベースのリキュールやスピリッツのジンも作っていますね。
リキュールは、薩摩のさつまの認証品も作られている農事組合法人 梅香丘さんの梅の実で造るんですけど、梅の収穫時期が大体5月ぐらいなんですよ。
なので、その時期に梅を収穫させてもらいに行って、梅を漬け込んだりっていう梅酒の製造時期になりますね。
ジンは、一部、国内では手に入らない素材(ハーブ)を除いて、それ以外は全てさつま町産の素材を使って造っています。
――芋焼酎をメインとしつつ、焼酎の他にもリキュールやスピリッツと様々な種類のお酒を造られていらっしゃいますね。その中でも生芋へのこだわりやさつま町産の素材を、というお話がありました。
こだわりの理由を教えていただけますか?
お酒の元となるものって、お水なんですよ。
焼酎でも基本的に25度のアルコール度数がありますけど、やっぱり大半は水分なので、地域のお水を原料に使っていれば、やっぱりこの土地で取れたものとの相性ってすごくいいと思ってます。
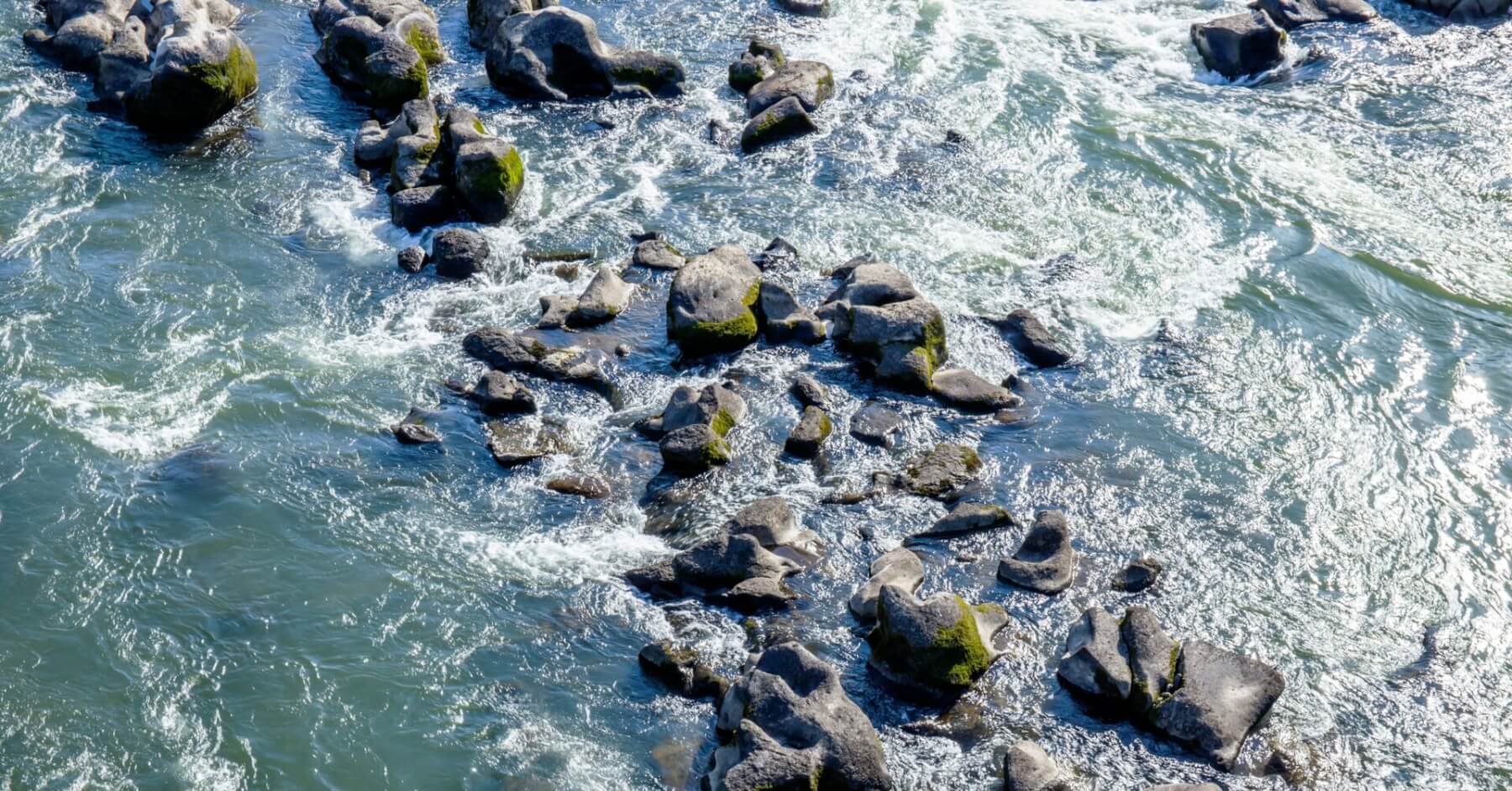
それに、僕たちはここで酒蔵をさせてもらってるので、”薩摩のさつま”ではないですけど、やはりこの町のものを使ってwin winの関係を作っていけたらなと。
例えば、梅酒を飲んだ人たちがこの梅おいしいねって言って梅香丘さんの梅を買ってくれたら嬉しいですし、やっぱりそういった繋がりを持ってやりたいので、できる限りさつま町産のものを使っていきたいなと思っています。
梅に関してはやっぱり梅香丘さんが丹精込めて作られてますし、普通に食べてもおいしい梅なんですけど、梅酒に加工することで普段と違うお客さんがこの梅を購入されたり、逆に梅香丘さんのファンが梅酒を購入していただいたり、そもそもさつま町に興味持ってもらったりとか。
だけど、僕らは物作りをさせてもらってる中で、やっぱり適当なものは使いたくない。
なので、「さつま町だから」使うんじゃなくて、「さつま町の良いものだから」使っていきたいので、町外ですごい方がいればそこの原料を使いたいと思いますし、だけど、それがさつま町のものだったら尚良しかなと思って、そういう方達と一緒にタッグ組んでやっていきたいなと思ってます。

――水を中心とした地域の素材へのこだわり。そして歴史と伝統が支える確かさが説得力として商品に宿るように勝手に想像しました。
一方で、普段焼酎やお酒に触れない方でも、ボトルやユニフォーム、ロゴ等の斬新なデザインに興味を持たれる方も多いと思います。
そのデザインの斬新さに、酒蔵として受け継がれ守るべき伝統と革新へのチャレンジ、という二極的なものを勝手に想像したのですが、革新へのチャレンジと言う点においてきっかけとなるようなものはあったのでしょうか。
うちは僕と弟が中心でやってるんですけど、弟がとにかく革新的な感じなんですね。
もちろん大事な屋台骨として受け継がれてきた伝統は紡いでいかないといけないんですけど、やっぱり新たに進化していかないといけないというところですね。

2009年に創業100周年をしたときには、僕と弟それぞれの名前から頭文字をとって「一尚」という芋焼酎を造らせてもらったんですけど、今までにない、清酒用酵母を使ったりビール用酵母を使ったりとかしています。
まあ、やってみないと良いか悪いかも評価できないですし。
だから、チャレンジっていう部分は、デザインの話に限らず、焼酎造りの中で常にやってる部分ではあるんですね。
例えば、この間、JPS(一般社団法人 J.S.P/ジャパン・サケ・ショウチュウ・プラットフォーム)っていう活動で日本酒とのコラボをさせてもらったんですけど、そういったことって今までの歴史はないんじゃないかなとは思うんです。
ただ、そこに走りすぎると大丈夫かってなってしまいますけど、そうやることで既存の焼酎造りをブラッシュアップしていったりとか、チャレンジしていかないと気付かないことだとかあると思うんですよね。
だから、この制服にしても、作ったきっかけは出会いが1番っていうところではありますけど…やっぱりこのさつま町ってやっぱり田舎じゃないですか。
その中で、ただの作業着でもいいんですけど、ユニフォームを作ることで僕らは一致団結もできるし、こういったファッションから焼酎造りのことを知りたいって思ってくれることもあるかなと。

紅小牧の赤いボトルに関しても、芋焼酎っていう言葉だけで毛嫌いしている人たちが中にはいるので、ボトルが可愛いとか、ちょっと気になるっていうところから口にしてもらえるきっかけにもなるかもしれないっていうところですね。
動き出せば、たぶん賛否両論はあると思うんですよね。
その中で整合性を持ちながら、表現できればいいのかなと思っています。
――今のお話にあったように多かれ少なかれチャレンジにはいつも「賛否両論」がついてまわるように思いますし、特に歴史や伝統があれば尚のことではと想像します。
その「賛否両論」に対して、どうやってバランスをとられてきたのかをお聞きしたいなと思っていました。
ただ、今のお話にもあったように、もちろん納得された上でだと思うのですが「やってみないことには分からない」ということを前提にまず歩んでみて、そこからまた1歩1歩確かめながら進んで行かれたということですね?
根本はやっぱりそこですよね。
もちろん納得した上でチャレンジしますし、今までたくさん失敗もありました。
ただ、そこは責任を取れる範疇での失敗という中でやらさせてもらっているわけで、その焼酎造りのチャレンジも、やっぱり酒屋さんがいらっしゃるから僕たちは成り立っているんです。

やってることは良いことだからこれは続けていかなきゃいけないと思うんだけど、だけど作るだけだとずっと在庫として溜まっていくでしょ、という話で。
僕たちの活動を良いも悪いも含めて、信頼っていうか、一緒になって二人三脚で歩んでくれる人たちがいるからこそ、僕たちはそういうチャレンジができます。
もちろん、怒られるというか…𠮟咤激励も当然あってですね。
だから、その蔵元と酒販店っていうのが上下関係でなく横の繋がりっていうか、僕たちはお酒を造るプロで、酒屋さんは売るプロとして対等な立場でできるからこそ、より僕たちもチャレンジできるっていうか、後押ししてもらっているっていうのはあると思いますよね。
――「なんでチャレンジできるんですか?」ということもお聞きしたいと思っていました。チャレンジできる理由は、まさに今のお話にあったように支え合う仲間がいるからなんですね。
そうなんです。チャレンジの限界はたぶん来るので。
そういうタイミングで、後押ししてくれる仲間たちがいるっていうのが、今に繋がっていることだと思うんですよね。

――“チャレンジ”という言葉だけを捉えると、主語は自分のみのように感じてしまいますけど、自分だけでは超えられない限界を、仲間が支えてくれるから超えられる。
さらにチャレンジしている姿を見て、仲間も自分のフィールドで限界へ挑む原動力に繋がるように感じます。
その仲間という点で、認証品『薩摩心酔 力三』には特別な味わいがあるように想像します。
なぜ『薩摩心酔 力三』を認証品としてエントリーされたのか、そのこだわりについて教えていただけますか?
やっぱり、薩摩のさつまには、焼酎”薩摩心酔 力三”(以下、力三)しかないですよね。
ただ、最初の頃は、薩摩のさつまを立ち上げるときから堀之内力三くん(以下、力三くん)が幹事長になるっていうことは当然分かってる中ではあったので、世間一般の目を考えたときに、力三を認証品にするのは避けた方がいいんじゃないかな、と思っていたんですよね。
だから、最初は別の商品をエントリーした方がいいかなって思ったんですけど、やっぱり薩摩のさつまっていう町が一丸となる取り組みで出すのはこの力三だなと。

そもそも、この力三ができたのは、薩摩心酔会っていう、蔵元、酒屋、飲食、一般の4者が集まる会を立ち上げたことがきっかけで、そこから、19歳の焼酎プロジェクトに発展していって、力三が出来たんです。(※焼酎”力三”は、19歳の焼酎プロジェクトで造られた原酒を新成人のための成人式や同窓会へ協賛として提供し、残った原酒を瓶詰し”薩摩心酔 力三”として販売している)
そのプロジェクトって、そもそも焼酎を作ることが目的じゃなくて、町おこしとか、もっと町を明るくするとか、この町を変えるって言ったらおこがましいですけど、良くしていきたいっていう力三くんの想いがあって、そこに感化された僕や色々な方との出会いがあって、こうして少しずつ輪が広がっていった経緯があるんです。
そういう歴史があったので、やっぱりさつま町が一丸となる薩摩のさつまっていうブランドの立上げも、なんか重なるものがありますよね。
だから、力三を認証品として出すのが1番分かりやすいと思うんです。
農家さんも堀り手の19歳の子も町の方ですし、そこに携わってる想いというのが半端ないので、力三を選んで良かったかなと僕は思っています。

――『薩摩心酔 力三』はその成り立ちが他のお酒とは違うのですね。
基本的に力三は、うちのラインナップの中では一般的に言うとPB(プライベートブランド)って言われるんですけど、僕たちはあれをタウンブランドって呼んでるんですよ。
タウンブランドっていうのは、町ぐるみで作り上げた商品のことで、例えば酒屋さんやうちが儲かるための営利目的で作った1本ではなくて、色んな人を巻き込んで出来上がった1本。
その1本をとおして町をより良くしていこうっていう想いが色濃い商品なんですよね。
だから今年も、コロナの状況次第ではありますけど、11月に芋掘りをして仕込み体験をさせてもらおうと思ってますし、来年4月には、その年に収穫する芋の苗植えを新成人の子たちがやってくれて、その苗から成長した芋を次の年の新成人の子たちが収穫するっていう形で紡いでいっています。
初めてやったときは、芋掘りと仕込み体験だけを予定していたんですけど、そのときに参加してくれた子たちが、次の年代の子たちにバトンを繋げるために「僕たちが芋の苗植えをしていいですか」って言ってくれたので。
その年代の子たちが次の子たちにタスキを渡すみたいな感じで、僕らが表現したかったことが、そうやってまた繋がっていったなと。
なんか、物語になってるみたいだなって、すごく思いましたよね。

うちのメンバーもそうなんですけど、サラリーマンの家庭で育つと農作業をしたことがなかったりするから、例えば、お米って、田んぼで作れるの?畑で作れるの?とか。
そういう子ども達も含めて、田んぼに行ってバッタを追いかけるでもいいし、そういった経験をするのって、すごくいいことだと思うんですよね。
そういった場面を作れるこの19歳の焼酎プロジェクトっていうのは、やっぱりすごくいいことだなと思っています。
やっぱり近くで見て経験することで物事の中身が分かっていくというか、外から見てるだけじゃわからない部分もあるので、そこで一緒に経験することで得られる理解の深さってたぶん2倍も3倍もあると思うんです。
それで、それを経験した子ども達や親御さんとの繋がりが広がっていって、輪になって、さつま町に繋がっていくんだと思います。

――多くの人が関わって、世代を越えて人の手で形づくられるようなイメージですね。
人の手が形づくるという意味では、例えばおにぎりを想像するのですが、もちろん機械で大量に作ったおにぎりも美味しいんですけど、一方で、僕は人が手で握ってくれたおにぎりって、すごく味わい深くて好きなんですね。
塩味とか成分的には分かりませんけど、その人を感じるところも「美味しい味」に含まれるというか。
もちろん、焼酎はおにぎりのように手で整形するものではないですけど、造り手という意味では、世代も超えた色々な人が手で形づくっているという意味では同じなのでは、と思います。
そこはもう間違いなく。
人間っていうのはたぶん官能っていうところでは色々味わいが違って当たり前なんですけど、例えば、酒屋さんが2軒並んでいて、どちらにもうちの同じ商品があるとしますよね。
それでもやっぱり、ここのお店のこの人から買うお焼酎がやっぱり美味しいっていうのはあると思うんですよ。
やっぱり嫌な人と一緒に飲んでたら、自分が好きなものでも味気がなかったりしますし、でも気心知れた人と飲むお酒っていうのはまた格別に違いますし。
味わいというか、スパイスじゃないけど、その違いはありますよね。
愛情がこもってるっていうか、確かに味は変わるよなと。

――「あじわい」って不思議ですけど、優れた言葉ですよね。
その様々な人の手が関わるタウンブランドには、世代を越えたバトンも紡がれているというお話もありました。
その次世代や未来についてもお聞きします。
薩摩のさつまには、次世代の支援といった未来へ向けた取り組みも含まれていますが、この地域ブランドを通して、子どもたちや未来の町がどうなってほしいといった想いはありますか?
僕としては、やっぱりさつま町の人口も増えていきたいし、やっぱり魅力溢れるっていうか、流動人口も含めてたくさんの方に来て感じてほしいって思いがあるんですよね。
それに小牧醸造としても、わざわざ来てもらえる蔵元になることで、さつま町に人が来てもらいたいって思いながらずっとやっています。
合併で宮之城町っていう名前がなくなってさつま町になって、いずれはさつま町が隣の薩摩川内市に吸収合併されて、みたいなのも嫌ですし。
やっぱり、このさつま町っていう町をしっかりと残していくために、僕たち世代が一生懸命、横の繋がりで守りつつ…いろんな人を巻き込みながら発信していくことで、いいものっていうか、感じてもらえるものっていうのをしっかりと伝えていきたいとは思ってます。
今でこそインターネットや県外の酒販店さんとか色んな方に支えてもらってますけど、でも数十年前までは僕らのお酒はこの地域でしか飲まれていなかったんですよね。
流通もなかったし。
そんな中で、周りの方たちが飲んでくださって、買ってくださったからこそ、今まで継続できてきたわけで。

まあ、昔は全然わかってなかったですけど、やっぱりそうやって、町外も含めてですけど、色んな人と出会えているのは、その紡いでくれた先代たちがいたからで、でもその先代たちを支えたのはやっぱり地域の人たちなので。
だからこそ、そこは感謝しつつ、僕たちができることを継続するっていうのが1番重要なことですけど、でもただ継続するだけじゃなくて、どうやったら喜んでもらえるかっていうところがまさにね。
そういったことが、僕たちができるさつま町への恩返しじゃないけど、いろんな近い人たちとタッグを組みながら、うちじゃないとできないことをやっていきたいなとは思います。
――流通としては地域外へも販路を広げたい一方で、人に関しては商品をつうじてその背景としての地域にも興味を持っていただいて、この地を訪れてほしいと僕も思っています。
その上であえてお聞きしたいのですが、商品を購入することだけを考えれば今はインターネットでも十分だと思います。
そこを、できれば現地へきてほしいという想いの背景をお伺いできますか?
例えば、全国の酒販店さんたちが集まるイベントを東京でさせてもらったりするんですけど、そこで、焼酎のお話をしたり実際に飲んでもらって、愛飲者の方や酒屋さん、飲食店さんとかと話をしながら、「是非ね、さつま町にも蔵を見に来てくださいよ」みたいな感じで話して来ていただけたりするんです。
もちろん、来てもらえなくても焼酎は買えますし飲めます。
だけど、僕だけじゃなくて、周りにいる、例えばうちのスタッフの子たちの顔も見てもらいたいし、10月みたいな製造時期であれば芋の表情だとか、作ってる活気とか匂いとか、そういうのを感じてもらうってすごく重要なんですよね。

それに、せっかく来てもらうんだったら、泊まってもらったり温泉に入ってもらったり、山のものとか川のものとか、さつま町って特産品が結構多いじゃないですか。
だから、そういうのを感じてもらったりとか。
やっぱりそういうことをして、毎年来てくれる飲食店さん達とかもいますし。
なんていうのかな、うちだけの魅力じゃなくて、力三くんもそうですけど、やっぱりこの周りの人たちの魅力を通してさつま町を見てもらいたいですね。
――確かに、現地の活気や熱気、造り手や風土を知ることで、結果的に味わい深くなりますし、おすすめする言葉にもリアリティが生まれますね。
そのように興味を持っていただけて、お金も時間も使ってわざわざ訪れてもらえる。
そして、例えば、最初は小牧醸造さんを訪れることが目的だった方も、温泉や食という地域との新しい出会いがあることで、きっと旅に広がりが生まれて、豊かさも持ち帰っていただけるように想像します。
そうですね。
でも、やっぱりそれはちょっとね、こっち側がプッシュしないと難しかったりするんですよね。
うちに来て終わり、みたいなことってやっぱり多いじゃないですか。
せっかく来たからいろんな行きたいという相手側の予定もあると思うので、そこにプラスアルファでこっちが手を差し伸べて、ちょっとあのお菓子屋さん寄ってよとか、ここへ泊まりに行ってみてよとか、昼飯だったらどこどこへとか。
相手任せにしてしまうと、うちだけの点で終わっちゃうんで、地域内に点を少しずつ増やしていって、それらを繋げて線にしていって、面にしていくっていう心持ちが大事かなと。
町外から来る人たちってなかなか情報もないから、きっかけを作ってあげないと。

――まさに薩摩のさつまでも目標の一つに掲げている「おとなりさんのソムリエ」の原点ですね。
1本の焼酎が中心になって広がる人の輪。
小牧醸造さんという酒蔵さんがあることで繋がる地域への広がり。
でも、その広がりの起点には、そっと手を差し伸べるようなきっかけが常にあるのでは、と想像しました。
関わる原料を活かし合い、人の手で、その味わいが一層深くなるようにきっかけを造ってあげる。
もしかしたら、お酒造りもまちづくりも本質は同じなのでは、と勝手に思ってしまいした。
今日は味わい深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。

※取材/撮影:青嵜 直樹(さつま町地域プロジェクトディレクター)
 認証品のご紹介
認証品のご紹介

小牧醸造株式会社『薩摩心酔 力三』
明治43年創業の老舗蔵が、故郷に暮らす方々と共にお芋を栽培し、共に芋焼酎を仕込み、身も心にも沁みる芋焼酎を創り上げました。農家、焼酎蔵、酒販店、愛飲家らが焼酎文化発展の為スクラムを組んで誕生した焼酎です。
一.地元農家さんの指導の下、春にはお芋を苗付けし、秋には収穫されたお芋を蔵に運び、焼酎を仕込みます。この畑から始まる焼酎造りを町民、子供達も一緒に行います。
二.一連の焼酎造りには「19歳の焼酎プロジェクト」も同時に行っています。年が明けた成人式での焼酎を自分達で仕込み、お酒の良し悪しも活動を通して学びます。
三.お酒は「喜怒哀楽」様々なシーンで寄り添ってくれます。そのお酒が故郷で生まれている喜びをこの焼酎を通して伝える事で、人を育み故郷の焼酎文化発展へ繋げたい。
ホームぺージ





